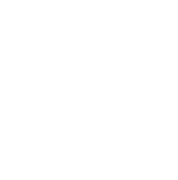荒木哲郎(監督)
- ――WITチームでは3作目の監督作になりましたが、荒木監督がこの『甲鉄城のカバネリ』でやりたかったことというのは、どんなものだったんでしょうか?
-
- 荒木やはり自分たちの物語を語りたい、自分たちがゼロを1にする仕事をしたい、というのが強くあります。前作の『進撃の巨人』は非常に手ごたえのある仕事でしたが、原作モノだったわけで、そうなるとある程度、原作の枠のなかで創作するという意識になる。原作をベースにしながら、自分が面白いと思うものを混ぜ込んでいくという作り方になるんです。とてもやりがいのある仕事でしたが、それだけをやっていると、自分で発想をする筋肉がいずれ弱まってしまい、原作ものの仕事に戻ったときにも、本当にみんなの助けになる存在にはなれない。だからオリジナルを作るのをやめてはいけないと。とはいえ『進撃の巨人』の仕事は、他人様の原作ではあるが、本当に自分が面白いと思うものをしっかり形に出来た仕事であり、そしてそれはちゃんと世の中に通じるじゃないか、という手応えがあった。であればそれを元手にして、今度はオリジナル作品という形で――それこそ『進撃の巨人』では扱えないような、例えば甲鉄城のようなメカニカルなものだったり、あとは可愛い女の子とかですよね(笑)。そうした要素を入れ込みつつ、自分たちが得意なアクションエンターテインメントをやってみよう、と思いました。
- ――「メカと美少女」というのは、日本の商業アニメが得意としてきたジャンルではあるんですが(笑)、『甲鉄城のカバネリ』にはそこにスチームパンク的な世界観だったり、敵としてカバネというゾンビが登場したりする。このあたりのビジョンの多くは、荒木監督の方から提案されたそうですね。
-
-
荒木とはいえ、最初からすべてが出揃っていたわけでもないんです。それこそ最初は、美少女主体で、アクションアニメーターが生きるストーリーで……というあたりから始まって、いずれゾンビものになり、いつしか時代設定を日本の中世――いわゆる時代劇にしよう、と。
-
- ――時代設定をそうしたのは何故でしょうか?
-
-
荒木一見、古臭く思えるものの方が、自分たちにとっては勝算が高い、と思ったからなんです。というのも――それは自分も含めてなんですけど、WIT STUDIOは職人集団の要素が強いので、「まだこの世にないものを発想して作る」よりは、「過去にあったものをしっかり調べて作る」ほうが得意なんです。絵柄に関しても、流行最先端というよりは、基礎的なカッチリしたものが得意ですから、それならむしろ古さの方に大きく舵を切って、一見、時代錯誤に思えるような方向で、じつは……という方が、自分たちの古臭さを長所に変えられるんじゃないかと思ったんです。今、「メカと美少女」と言われましたけど、『甲鉄城のカバネリ』は、一見、トレンドとは逆の方向に行っているかに見えて、じつはアニメファンが好きなものがいっぱい入ってる。そういう構造にしようというのが、企画者としての自分の目論見でした。
-
- ――例えば、オープニングの冒頭が生駒のセリフから始まるのも、一見、古臭く思えるけど、じつは……というポイントですよね。
-
-
荒木いまや誰もやらないくらい古くなってしまった手法を、あえて堂々とやることで、今のアニメにはないものを見つける。それはやっている間、ずっと念頭にあったことのひとつです。いわゆる温故知新じゃないですけど、そのOPのときには「『カムイ外伝』が行けるんじゃないかな?」とか(笑)。もちろんそれも、単純に古ければいいのかというと、そうじゃない。俺が好きじゃなきゃダメです。好きだからこそピックアップしようと思うし、俺が好きだと思っているということが、今の時代でも通用する何かの根拠になるだろう、と。逆に、好きでもないのにピックアップするのは、その手法に対して失礼だと思いますから。
-
- ――なるほど。ここからはストーリーについて少し伺いたいんですが、まずは主人公の生駒と無名ですね。この2人の組み合わせは、どこから発想されたんでしょうか?
-
-
荒木2人に関しては映画の『キックアス』です。……というか、『キックアス』的なものをやるという話は、ゾンビ物というモチーフが決まる前から「荒木が監督したら面白そうなもの」として、プロデュース側から提案されていたんです。ただ、そこからどうアレンジを加えていくかを揉んでいく段階で、俺から「ドラマ的には『タクシードライバー』の構造にします」という話をして。
-
- ――マーティン・スコセッシ監督、ロバート・デ・ニーロ主演の名作映画ですね。
-
-
荒木つまり、この世を僻んでいる青年が少女と出会って、彼女を苦しめているその主人をこの世の悪と見定めて倒す。そのときに自分の命を捨てる覚悟をするわけですけど、最後には生還する、という。『タクシードライバー』のストーリーを還元すると、こういう話になるわけですけど、それを今回の道具立てでやったら『甲鉄城のカバネリ』になったということですね。
-
- ――主人公の生駒は、監督自身のイメージが強く投影されたキャラクターだと思うんですが……。
-
-
荒木いや、むしろ生駒に関しては、俺ではないキャラクターにしようという気持ちの方が強かったんですよね。というのも、『ギルティクラウン』の主人公の集は「俺にしてやれ」と思って作ったキャラクターだったんですが、結果として視聴者から嫌われてしまった……と、俺は思ってて。もうちょっと人好きするというか、みんなに愛されるキャラクターになってほしかった。やっぱりキャラクターを好きになってもらえないと、そもそも話を見てもらえない。そこは『進撃の巨人』のときに強く感じたんですよね。『進撃の巨人』の原作者の諌山創さんは、キャラをイジめ抜く人だと思われてるかもしれないんですが、じつは「このキャラはみんなに愛してもらえるだろうか」って、すごく気にする方で。なるほど、キャラクターの人気こそがすべての商売の元になるんだな、と(笑)。そこで初めて、気づいたんです。なんかもう、みなさんにとっては「知ってるよ!」ってことだと思うんですけど(笑)。
-
- ――あはは。
-
-
荒木だから生駒はオタクっぽいし、みんなに対して僻む気持ちだったり、怨念めいた気持ちを持ってはいますけど、じつはキラリと光る才能なりを持っていて、しかも愛嬌がある。そういうキャラクターにしなければ、と。例えば『タクシードライバー』のトラヴィスは、怖いというかキモい(笑)。そこがあの映画の非常に面白いところではあるんですが、アニメのお客に対してはハードルが高い。だからあの心を持ちつつも、愛嬌が欲しいんだよね……というような話をしていたら、嫁から「それって『桐島、部活やめるってよ』で、神木隆之介くんがやってた前田だよね」と言われたんですよね。すごくヘンなことを言ってるんだけど、観客は可愛げがあるヤツだなって、応援したくなる。だから、それ以降は生駒を説明するときに「『桐島』の前田で」という話をしてましたね。可愛いヤツなんですよ、こいつはって(笑)。
-
- ――その一方で、例えば生駒のセリフは妙に生々しいところがありますよね。
-
-
荒木そうですね。「俺みたいなキャラにしよう」とはまったく思っていなかったんですけど、やっぱり主人公なので、それなりに腰の入ったセリフにしようと思うと、結局、自分の肉声じゃなきゃ説得力を持たせられない。だから折に触れて吐くセリフは、結局のところ、俺なんですよ。……例えば、第11話の生駒なんて、まさに俺そのもので(笑)。「最初から何もするべきじゃなかった」って生駒のセリフとか、嫁から「完全におまえだ」って言われたくらいなんですけど(笑)。
-
- ――あはは! そんなことがあったんですか。
-
-
荒木ドン底まで落ちて、そこから這い上がるという話にしたかったので、であれば、徹底的にヘコませなきゃダメだろう、と。あの落ち込んでいる生駒のモデルって、じつは太宰治の『走れメロス』のメロスなんです。高校時代、俺は太宰治がすごく好きだったんですけど、落ち込んでいると、自分が信じていた友達のことまで疑い始める、みたいな感じが好きで(笑)。『ギルティクラウン』のときもそうだったんですけど、だいたい高校時代の怨念みたいなものを、作品に埋め込んで、成仏させようとするきらいがありますね。
-
- ――では最後に、作り終えてみて、手応えはいかがでしたか?
-
-
荒木今回もいい仕事をさせてもらえたと思っています。オリジナル作品を作るという仕事はいつも一筋縄で行きませんが、前回よりもう一段上に行けたと思っています。 とはいえ、短いシリーズだったんで、この企画のキャパシティを、まだ全開放させてあげられていないという意識も強くあります。まだまだやりたいシーンもあるし、使ってないネタもたくさんある。この器は結構、強いし広いってことをお見せしたい。そのためにも次の場が欲しいですね。いいキャラクターを作れたんで、お客さん同様、自分も「あいつらにまた会いたい」とも思ってますので、皆さん応援よろしくお願いします!
-